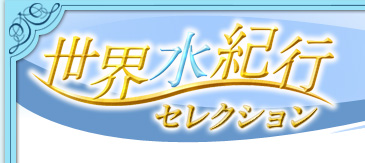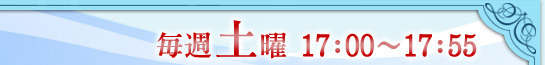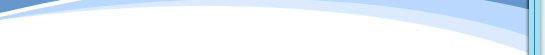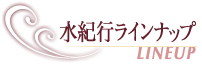


2014年3月12日 放送


インドシナ半島の内陸に位置するラオス人民民主共和国。
北部の「ルアンパバーン」はかつて都が置かれた町で、
メコン川のほとりにおよそ2万9000人が暮らしています。
小さな町には60を超える寺院があります。
そのひとつが、町のシンボル「ワット・シェントーン」です。
1560年にラーンサーン王朝の王によって建立されました。
ラオスで最も美しい寺院と言われる本堂。
湾曲した屋根の造形が当時の「ルアンパバーン建築」の特徴です。
本堂の壁には、20世紀の職人による装飾が施されています。
「マイ・トーン」という黄金の木。
かつてこの場所に立っていたという高さ160メートルもの伝説の大木が
モチーフで、仏教にまつわる様々な物語がモザイクで表現されています。
早朝。町では、ラオスの人々の仏教への強い信仰を示す光景に出会えます。
托鉢です。
僧侶たちが町を練り歩き市民から供物を受け取ります。
僧侶の生活費を大衆が賄うというのが、上座部仏教の大きな特徴のひとつです。
信徒はこうした功徳を積む事で来世の幸福を祈ります。


町を流れるメコン川では、ルアンパバーン周辺を巡る観光クルーズが人気です。
山間の町ルアンパバーンの周辺には、
今もアニミズムの精霊が宿る自然が豊かに残っています。
川沿いには小さな村々が点在していて、メコンの伝統の暮らしを
垣間見ることができます。
その村のひとつ「バーンサーンハイ」は、
ラオスを代表する焼酎「ラオラーオ」で有名な村です。
アルコール度数は50度以上で、地元ではストレートで飲まれています。
2週間ほどかけて発酵させたモチ米を、醸造のためにドラム缶に入れます。
季節や湿度によっても味に変化が出るため、
その時々で火加減水加減を調整しています。
伝統の地酒「ラオラーオ」。彼らの言葉で頭の「ラオ」は「酒」を、
そして、後ろの「ラーオ」は「ラオス」を意味します。


ルアンパバーンから南東へおよそ1000キロ。
「パクセー」は南ラオスを代表する大都市です。
タイやカンボジアとの国境に近いことから、ラーンサーン王朝以前から繁栄してきました。
パクセーの郊外に、プーカオという山の中腹に世界遺産の遺跡があります。
7世紀ごろに建てられたとされる「ワット・プー寺院」の遺跡です。
ワット・プー寺院は、古代クメール人が建造したと言われています。
クメールは、東南アジア各地に分布する民族で、
ヒンドゥー教を信仰していました。
かつては同じヒンドゥー教の聖地アンコールワットと一本道で
繋がっていたといわれています。


ラオス南部では、穏やかに流れていたメコン川の様相が一変します。
「コーンパペンの滝」は、その激流から、「メコンのナイアガラ」とも
呼ばれています。
大河メコンは、コーンパペンの滝の難所を経て、国境の先カンボジアへと
流れ込みます。


苦難の歴史を歩みながらも祈りと微笑みを絶やすことが無いといわれる
ラオスの人々。その彼らがよく口にする言葉があります。
「ボーペンニャン」…大丈夫、何でもないという意味です。
「母なる大河メコンがある限り大丈夫」
そんな思いを胸に
ラオスの人々は今日も穏やかに生きています。