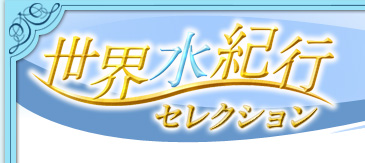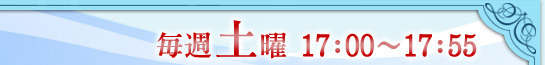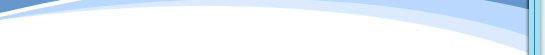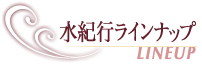


2014年1月15日 放送
アラビア海を望む、インド西海岸の港街「ムンバイ」。
金融、商業の中心地であり、宗教や文化の面でも重要な位置を担います。
17世紀、当時のポルトガルの王女がイングランド王に嫁ぐ際に持参金として献上されたムンバイの街。
市内には、当時建てられた英国風建築が数多く残っています。

なかでも、その時代を代表する建物があります。
チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅です。
2004年に、鉄道の駅舎としては初めて世界遺産に登録されました。
完成したのは1888年。
イギリスのヴィクトリア・ゴシック様式の傑作として知られ
現在も、一日に300万人以上が利用しています。


アラビア海を望む水辺に、一軒の美しいホテルがあります。
ザ・タージ・マハール・パレスです。
オープンは1903年。
かつて、あるインド人男性が高級ホテルに入ったところ、
白人でない事を理由に宿泊を断られました。
この事に激怒した男性は、もっと豪華で誰でも宿泊できるホテルを
インド人の手で建てようと決意したのです。
その男性が創業者のジャムシェトジー・タタ。
国内最大の財閥、タタグループの創始者で、「インドの産業の父」と呼ばれています。
旧館のシーラウンジは、世界最高とも言われるインド人執事のサービスで
ハイ・ティーが楽しめます。
ハイ・ティーは夕方遅い時間のティータイムで、イギリス統治時代に伝わりました。
インドは世界一の紅茶の産出国です。
シーラウンジでは、30種類もの国産の紅茶を取り揃えています。

インド西部の港街ムンバイ。街の海の玄関口がインド門です。
1911年、統治国であるイギリスの国王ジョージ5世が
妻と共にこの地を訪れたことを記念して建てられました。
インド門の下の桟橋から、遊覧船が出航します。


ムンバイの東10キロの海に浮かぶのが、エレファンタ島です。
16世紀にポルトガル人が初めて上陸した時に、
古代インド王朝の象の石像を見つけた事から名付けられました。
島の高台に、岩山を掘ったヒンドゥー教の寺院があります。
エレファンタ石窟群です。
1987年に世界遺産に登録されています。
寺院は7世紀ごろの古代インド王朝が作ったとされています。
壁には、ヒンドゥー教の神、シヴァ神の一生を描いた石像が彫られています。
シヴァ神は破壊を司る最高神です。
暴風雨を操り、破壊的な風水害をもたらす一方で
土地に水を与え、植物を育てる力ともなります。
これらの石像は、文字が読めない人にも
ヒンドゥーの教義をわかりやすく伝える為に彫られたと言われています。


ムンバイから南へおよそ1000キロ。
コーチは水郷として知られる、インド南部ケララ州の古い港街です。
「ヤシの木」を意味するケララの名前の通り、
いたるところに天然のヤシが茂っています。
ここは果物や米、香辛料の産地としても知られています。
アラビア海沿岸で最大の港を持つコーチの街。
1世紀に多くのユダヤ人が移住をはじめ、
古代ローマやエジプト、ギリシャ諸国からも人々がやって来ました。
そして当時「黒い黄金」とも呼ばれた黒胡椒などの香辛料の取引が盛んになりました。

コーチの水辺で見られる独特の風景。
これは、チャイニーズ・フィッシング・ネットです。
岸辺の魚を獲るための漁法で、かつて中国の貿易商によって伝えられました。
水揚げされた魚は、そのまますぐに港の魚市場に持ち込みます。
観光地としても人気のコーチの街。
市場で買った魚を近くのレストランで調理してもらうこともできます。

港街コーチから、南へおよそ65キロ。
アレッピは運河が縦横に走り、「東洋のベニス」と呼ばれています。
アラビア海沿岸に広がる、バックウォーターは
無数の川とその支流、そして水が運んできた土砂が作るデルタ地帯です。
バックウォーターの名物が、ハウスボートと呼ばれる船です。
水の上の宿泊施設で、中には高級ホテル並みの設備の船もあります。
インド国内で最も牧歌的とされる自然と、そこに暮らす人々の風景。
ケララは「神の国」とも呼ばれています。
運河の両岸に、稲作の田んぼが広がります。
ケララ州は、インド有数の米の産地です。



バックウォーターは海水と川の水が混ざる地域にあり、
エビやカニ、雷魚の一種がとれます。
この辺りの人は、半農半漁の生活を送っているのです。

インド南部を代表する港街コーチから、南へおよそ220キロ。
国内有数のリゾート地があります。
マナルティーラム・アーユルヴェーダ・リゾート。
69軒のコテージからなる、リゾート施設です。
「生命の科学」を意味するアーユルヴェーダ。
その施術は専門の医師の診断のもとで行われます。
問診の後には脈拍や血圧も測られ、その人にあった施術が行われます。
シロダーラは、額の最も敏感な部分に一定温度のオイルを垂らし続けて
一種の瞑想状態にする治療法で、別名「脳のマッサージ」と呼ばれています。
古代インドを発祥として、5000年の歴史を持つというアーユルヴェーダ。
その治療は生活全般に及び、「より良く生きる」ということを目的としています。