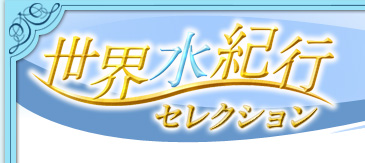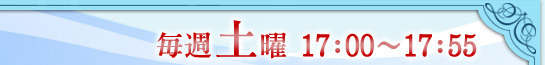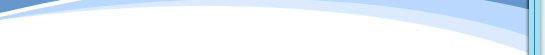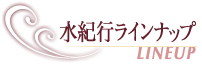


2015年3月18日 初回放送
1万3000以上もの島々からなるインドネシアのほぼ中央部。
赤道直下に位置する「スラウェシ島」。
4つの半島で形作られた島の北端に位置するのが港町の「マナド」です。
古くから香辛料の貿易で栄え、現在もスラウェシ島第2の都市です。
インドネシアは国民の大半がイスラム教徒ですが、スラウェシ島は人口の7割がキリスト教徒です。大通りに沿ってヨーロッパ風の教会が建ち並んでいます。


古くから貿易や交通の要衝とされたマナドの町は、今も海が人々の生活を支えています。
地理的条件から開発が進まず、牧歌的な雰囲気が魅力のマナドの海辺は
リゾート客に人気があります。
エメラルドに輝く手つかずの海は、世界中のダイバーの憧れとなっています。


マナドの町からから南東へおよそ30キロの地点にある「トンダノ湖」は
スラウェシ島を代表する観光スポットです。
面積が日本の芦ノ湖のおよそ6倍にも達する巨大なカルデラ湖で、
コイなど淡水魚の養殖が盛んです。
この湖で代々、養殖業を営んできたクラウディオさん。
現在クラウディオさんの養殖場では、「ムジャイル」というスズキの仲間の淡水魚など、20万匹ほどの魚を育てています。


スラウェシ島の北部。「マナド」から東へおよそ50キロに位置する港町「ビトゥン」。
貨物船が行き交うインドネシアを代表する海の玄関口で、
古くから漁業の基地として知られています。
ビトゥンはカツオ漁とその加工技術で栄えてきました。
インドネシアが世界一の漁獲量を誇るカツオは、
ビトゥン市内のカツオ加工工場で日本人にとって馴染み深いある食材に加工されます。
「鰹節」です。
ビトゥンがカツオの町となったのは第二次大戦前。日本人が設立した鰹節工場が最初だといいます。終戦とともに一旦、鰹節工場は消滅しましたが、1970年代に入って、かつて工場で技術を学んだ現地の人々が鰹節作りを再開したそうです。


スラウェシ島中央部の高原地帯「タナ・トラジャ」。
トラジャ族の集落には、高床式の独特なデザインの建物が並んでいます。
トラジャ族の伝統家屋「トンコナン」です。
船のような形で、屋根が船の舳先のように空に向かって反り返っています。
船の形をした家屋は、海洋民族としてのアイデンティテイーを、子孫に伝えるためといわれています。


タナ・トラジャ一帯は世界的に有名なあるコーヒーの産地としても知られています。
「幻のコーヒー」とも呼ばれるトラジャ・コーヒーです。
トラジャ・コーヒーはこのタナ・トラジャ周辺の高地だけで栽培されていて、
かつてはオランダ王室にも献上されていました。
苦味と深いコクが特徴のトラジャ・コーヒー。
戦前の隆盛、戦中の危機、戦後の復活、という、
スラウェシ島とコーヒー豆が辿った歴史が香ります。