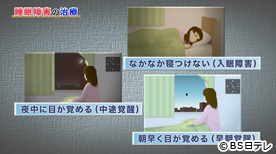医進薬新 夢のメディ神殿2018スペシャル

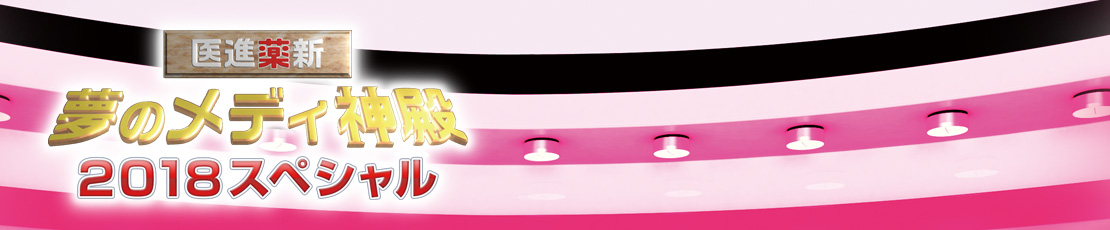
第4回 睡眠障害
2018年02月04日 初回放送
<今回のテーマ>
不眠をはじめとする睡眠障害は様々なものがあり、背景も多様です。
睡眠障害が続くと、「うつ病」や生活習慣病の「高血圧」「糖尿病」などのリスクが高まります。
様々な研究が行われる中、不眠に関わる重要な神経伝達物質「オレキシン」は日本人グループが発見。
オレキシンの発見により、睡眠と覚醒のメカニズムが解明され、新薬が誕生しました。
<睡眠障害とは>
睡眠障害は90以上の疾患に分けられると考えられ、代表的なものが不眠症、睡眠時無呼吸症候群などです。
<不眠症>
不眠症は男性17.3%、女性21.5%と女性に多いというデータがあり、年を取るとともに高くなり、80歳以上では男性30.5%、女性は40.3%に達し、高齢者の3人に1人くらいが不眠を訴えています。
主なものは、なかなか寝つけない「入眠障害」、夜中に目が覚める「中途覚醒」、朝早く目が覚める「早朝覚醒」などです。
不眠症が続くと、うつ病や生活習慣病の高血圧、糖尿病、高脂血症などのリスクが高まり、さらに、認知症のリスクも高くなると言われています。
<不眠症の治療>
まず、睡眠時の留意点について医師が指導。
・就寝前にカフェインを摂らない ・眠くなるまで布団に入らない
・毎朝、同じ時間に起きて太陽の光を浴びる
・規則的な運動習慣など、生活習慣を見直すことから始めます。
それでも改善しない場合は、睡眠導入薬が処方されます。
<2014年 新たな睡眠導入薬が登場>
今までは、脳の興奮を抑えて神経伝達物質の働きを促したり、睡眠のリズムを作る体内時計を整える薬などで治療をしていましたが、2014年「オレキシン受容体拮抗薬」が登場しました。
オレキシンとは、脳内の信号を伝える神経伝達物質です。
オレキシンの分泌量によって、覚醒と睡眠のONとOFFが切り替わります。
この仕組みを利用したのが、「オレキシン受容体拮抗薬」です。
<神経伝達物質 オレキシンは世界的な大発見>
睡眠と覚醒のONとOFFの切り替えに重要な働きをしているオレキシンは、日本の柳沢正史教授を中心とした研究グループが発見。
柳沢教授が、発見の経緯を語ってくれました。
現在も柳沢教授は研究所の責任者として、世界トップレベルの研究者を集め睡眠研究を行っています。
出演者
- 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 院長
- 精神神経科
伊藤 洋(いとう ひろし)教授
- 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構
- 機構長
柳沢 正史(やなぎさわ まさし)教授